

この記事ではエニアグラムの“健全度”の基礎を説明します!
(特に「不健全さとは何なのか?」について説明します。)
人の持つ“価値観”だけでなく、“健全度(精神状態)”によって人の性格状態を説明できるというのは、エニアグラムの魅力の最たるところだと思ってます!
ではいきましょう!
エニアグラムの“健全度”(発達の諸段階、成長レベル)とは?
とは?.jpg)
「同じ性格タイプだと思うのに、まったく違う人に見える…。」
ってこと、ありませんか?
(もう少しハッキリ言うと…、「同じ性格タイプなのに、なぜ“良い人”と“嫌な奴”がいるのか?」と、疑問に思いませんか?)

その疑問に答えてくれるのが、“健全度”という考え方です。
エニアグラムが説明してくれる人の9つの性格は“価値観”の違いですが、
同じ価値観の中でも、「“精神状態”が異なれば表れる態度は異なる」という考えが“健全度”です。
エニアグラムではこの“精神状態”の違いを、「“発達の諸段階”、“成長レベル”、“健全・不健全”」などと呼びます。
(以降は“健全度”の言い方で統一しますね。呼びやすいので。)
この“健全度”は大きく3つのフェーズ(“健全”・“通常”・“不健全”)に分けられ、さらに各フェーズが3つに分類されます。
よって、全部で9段階に分けることができます。
9段階.jpg)
つまり、「9種の価値観×9段階の健全度」で、人の性格を81種類の状態に分けることができるということです。
(同じ価値観の中でも、ウイングを考慮すればさらに2種類に分けられることを考えれば、正確には162種類に分けられます。)
ただ、いきなり細かい話をしても難しいと思うので、この記事ではまずは“エニアグラムの健全度”についての基礎として、基本的な3つのフェーズ(“健全”・“通常”・“不健全”)の違いにフォーカスして解説したいと思います。
.jpg)

もし「基礎はもう分かるから、9段階の健全度について教えて!」という方がいれば、こちらを参考にどうぞ!
>>“エニアグラムの9段階の健全度”とは?(※上級編)
(…でも、基礎編から読む方が、理解は進むと思いますよ!)
エニアグラムの“不健全さ”とは??

エニアグラムの健全度を理解する上で、もっとも近道なのは、
「“不健全さ”とは何なのか?」
を知ることです。
とういうわけで、まずはそこから確認していきましょう。
結論から言うと、
「不健全さとは、自分の性格タイプ特有の思考・行動パターンから抜け出せなくなる状態」
です。
ここでイメージしやすいように、各性格タイプが不健全なときに「何を恐れて、どんな反応をするのか」という代表的なパターンを紹介しましょう。
- タイプ1「自分は間違っている」と恐れて、批判的で完璧主義になる。
- タイプ2「自分は愛されない」と恐れて、恩着せがましくお節介になる。
- タイプ3「自分には価値がない」と恐れて、見栄っ張りで成果至上主義になる。
- タイプ4「自分は独自性がない」と恐れて、人に否定的で気分屋になる。
- タイプ5「自分は無能で役に立たない」と恐れて、知識ばかりの皮肉屋になる。
- タイプ6「自分には支えがない」と恐れて、保守的で疑心暗鬼になる。
- タイプ7「自分は満たされない」と恐れて、移り気で飽き性になる。
- タイプ8「自分は支配される」と恐れて、怒りやすく威圧的になる。
- タイプ9「自分は平和でいられない」と恐れて、葛藤を避けて堕落する。
ここまで読んでみて、
「パードゥン?」
と思っている方、安心して下さい。笑
ここから、ちゃんと詳しく説明してきます。

“不健全”の説明をする上で、まず、エニアグラムの権威であるリソ氏とハドソン氏の言葉を引用します。
「私たちは不健全になるとき、(中略)自動的反応と幻想の迷路に囚われ、コントロールを失います。強まる恐れや葛藤、そして直面するいかなる実際的問題に対しても、解決を見いだすことができません。(中略)あまりにも性格の限定されたメカニズムに同一化してしまうために、他の解決方法が思い浮かばないのです。」
(リソ&ハドソン. エニアグラム あなたを知る9つのタイプ【基礎編】)
“不健全=性格の限定されたメカニズムに同一化”
ということですね。
「…ちょっと何言っているのか分からない」
という方、大丈夫です!笑
補足していきますね。

まず、エニアグラムの“不健全”の説明を理解するには、前提として、
「エニアグラムが、“性格”というものをどう認識しているのか」
を、知っておく必要があります。
そこで、リソ&ハドソンの同著より、もう1カ所引用します。
「エニアグラムのねらいは、「気づくこと」により、性格の自動的反応を止めることです。(中略)性格からくる自動的反応をみることができればできるほど、私たちはそれと一体化(同一化)することが減り、より自由になるのです。」
(リソ&ハドソン. エニアグラム あなたを知る9つのタイプ【基礎編】)
“エニアグラムの狙い=性格の自動反応を止めること”
ということです。
これを読むと、“性格(の自動的反応)”というものが、ネガティブな印象で語られていることに気付くはずです。
これも踏まえて、解説していきます。
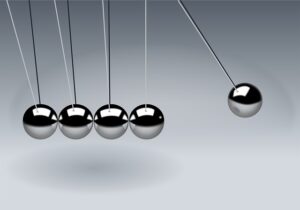
まず、ここまでに登場した「性格の限定されたメカニズム」と「性格の自動的反応」は、ほぼ同じ意味です。
そしてこれらは、エニアグラムで示される9種類の“性格タイプ別の行動パターン“のことを指しています。
(※異なる言葉を使っているので正確には差異はあると思いますが、今は一旦爽やかに置いておきます。笑)
そして、“性格別の行動パターン”に対しては、次のように言われています。
- 不健全な時には「同一化してしまう」もの。
- そもそもエニアグラムの狙いは、これを止めること。
要するに、“不健全な状態”とは、“性格タイプ別の行動パターンから抜け出せない状態”と言えるわけです。

そう考えると、エニアグラムの各性格特徴を知って、自分がよくやる思考・行動パターンに気付けるだけでも、“健全”に近づけると言えるかもしれません!
エニアグラムの“健全度”の3つフェーズの状態の違いは?(“健全・通常・不健全”の特徴!)

さて、ここまでで次のことを整理しました。
- “健全度”とは、“精神状態”。
- “不健全な状態”とは、“性格タイプ別の行動パターンから抜け出せなくなること”。
それを踏まえて、ここから「健全・通常・不健全」の状態の違いについて、説明していきましょう。
“健全度”のイメージは、“性格”という“装備”による“防衛力”の高さ!

“健全度”を理解する上で知って欲しいことは、「“不健全”な程に、恐れに対する“防衛力”が増していく」ということです。
つまり、私たちは「自分を守りたい」と思うほど、自分の性格の殻を厚くしてしまうということです。
ここで言う“殻の厚くなった性格”こそが、先に紹介した「性格の限定されたメカニズム」であり「性格の自動的反応」であり、“恐れからくる行動パターン”のことです。
これは「自我」と呼ばれることもあります。
エニアグラムでは、「“自我”の中に“本質(≒本来の自分自身)”がある」という考え方をするので、「“自我”=“防衛力”=“装備”」とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

これが“不健全”になるほど、装備は厚くなり、装備と一体化していく(ガチガチになっていく)イメージです。
(※ここから少し、“不健全”の例え話が妄想的に膨らむので、ヒマな人だけお付き合い下さい。)

近未来―。
荒廃した街の中では、ロボット兵たちによる激しい戦いが繰り広げられている。
そんな中、街から少し離れた丘の上に、ぎこちなく歩く1体のロボット兵が見える。
ボロボロになった装甲が戦況の厳しさを物語る一方で、鈍く光るアーマーの電気信号が“闘う意思”はまだ残っていることを示している。
ロボット兵は、周辺を警戒しながら、ゆっくりと腰を下ろし、恐る恐るヘルメットを開けていく…。
中から現れたのは生身の人間で、しかもそれはまだ年端もいかない少女だった。

分厚いアーマーに守られていたはずなのに、それでも顔は傷付いていて、その表情は憔悴しきっている…。
次の瞬間、
「ドゴォーー…ン!」
と、街の方から激しい爆発音が聞こえる。
少女はすぐさまヘルメットを再装着し、機械的な動きで街へと走って戻っていった。
※「ロボットアーマー(装備)」が自我(=防衛力)で、「生身の人間(少女)」が本来の自分(=本質)で、「荒廃した街」が社会(職場や学校など)で、「街から少し離れた丘」が一人の時間や大切な人といる時間で、「爆発音」がストレス刺激だと変換して読んで下さい。
“不健全”のイメージの参考までに。
“不健全”になると、なぜ“防衛力が増す(自我と同一化する)”のか?
?.jpg)
では、なぜ「不健全になるほど恐れに対する“防衛力”が増していく」のでしょうか?
それは、「恐れを解消するための行動が機能せず、恐れが強まっていく」という悪循環にハマっていくからです。
(不健全になるほど、自分の行動パターンから抜け出せなくなっていくというのは、地獄ですよね…。)
その悪循環のイメージを、分かりやすくなるように“メンタル面”と“行動面”に分けて図にしてみました。
-1024x507.jpg)
(※補足:本来は、メンタルと行動は繋がっているので、2軸で分ける要素ではないですが、ここではどっちも満たされない泥沼さが不健全さの肝であることを伝えたくて示します。
メンタル(恐れと欲求)と行動(態度と行為)の正しい関係図は、上級編で紹介します。)
さて、ここまでの話から、“健全”と“不健全”の概観はつかめてきたんじゃないでしょうか?
最後に、“健全・通常・不健全”のそれぞれの状態について、さらに具体的に説明しておきましょう。
エニアグラム“健全”の段階の特徴は?
イメージ.jpg)
- メンタル:欲求にこだわらない。(ある程度満たされている。)
- 行動:自分の資質(性格的な強み)を社会に活かせている。
- “自我”との関係:気付いて手放せている。(距離を置けている)
“健全”の状態にある人は、一言で言うと、“ゆとり”があります。
周りからも、「バランスが取れていて、能力が高い人」に見える場合が多いです。
この状態の時は、資質(各性格タイプの欲求を満たすために得意とする行動)を、建設的に発揮できているのも特徴です。
この“健全”状態を一時的に経験したことがある人はたくさんいると言われますが、この状態を維持できる人はレアだと言われています。
エニアグラム“通常”の段階の特徴?
イメージ.jpg)
- メンタル:時に満たされ、時に満たされない。
- 行動:建設的(前向きな動機)な場合と、防衛的(後ろ向きの動機)な場合がある。
- “自我”との関係:とらわれている。
“通常”の状態にある人は、自分の性格タイプ別の“欲求”を満たすために、“お決まりの行動パターン(各性格タイプの“恐れ⇒欲求⇒態度⇒行為”)”が表れます。
つまり、エニアグラムで一般的に説明される“各性格タイプの特徴”が、顕著に表れる状態だと言えます。
(そもそも、ほとんどの人はこの“通常”の段階に位置すると言われています。だから、エニアグラムで説明される性格タイプ別の特徴は、この“通常”段階の特徴を説明していることが多いです。)
とは言っても、比較的にメンタルは安定しています。
調子の良い時は、行動が建設的に活きて、欲求は満たされ、
調子の悪い時は、行動が防衛的になり、欲求が満たされません。
つまりは“普通”ですね。笑
ただし、そういった“波”があることによって、対人関係においても適度な葛藤を感じることになります。
エニアグラム“不健全”の段階の特徴は?
イメージ.jpg)
- メンタル:欲求を満たせてない。(渇望し、葛藤している。)
- 行動:行動パターンが空回りしている。でも、止められない。
- “自我”との関係:固着している。(抜け出せなくなっている。)
“不健全”にあるとき、自分の欲求を満たすことへのこだわりが増す一方で、それを満たす手段が粗くなり、空回りするようになります。
よって、ストレスに上手く対処できず、些細な刺激にでも大きく反応してしまうようになります。(もしくは、諦めてしまう。)
そしてさらに、ストレスに対処するための行動が、お決まりの特定パターンに固定化されていくので、行き詰まって抜け出せなくなっていきます。
そうして、自分で欲求を満たせなくなると、代わりに人に解決させるように求め出します。
(他責思考・他者依存の“困った人”になってしまうわけですね…。)
ちなみに、“不健全”な状態に留まり続けることもあまりないと言われています。
なぜなら、“不健全”まで落ちた後は、改善に向かうしかないからです。
…あるいは、破滅してしまうとも言われています。
(「破滅」って、怖いですよね…。具体的には、“重たい精神病”にかかったり、あるいは“取返しのつかない事件”を引き起こしてしまったりなどです。)
ただ、そもそも、“不健全”な段階にまで落ちるのは、よほどの時だとも言われています。
(例えば、大病、愛する人との死別、失業など。)

“不健全”な状態って、こわいですよね…?
ここで、ガクブル怯えているあなたに“耳より情報”があります!
噂によると、「健全度が落ちる間際には、ストッパーとなる信号(感覚)が働く」というのです。
詳しくはこちらをどうぞ!
>>エニアグラムの“目覚めの注意信号”と“危険信号”を分かりやすく解説!


.jpg)
を分かりやすく解説!.jpg)
.jpg)
